「生活水準」を考える旅・・・バングラデシュ
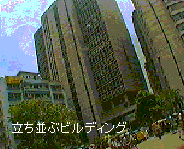 生まれて初めての飛行機、そして生まれて初めての海外旅行が、実はバングラデシュであった。友達が海外青年協力隊でバングラデシュにいて、そこを3人で訪問したのだった。見るものすべてが新しく、感動の連続だった。
生まれて初めての飛行機、そして生まれて初めての海外旅行が、実はバングラデシュであった。友達が海外青年協力隊でバングラデシュにいて、そこを3人で訪問したのだった。見るものすべてが新しく、感動の連続だった。
バングラデシュといえば、世界で最も貧しい国のひとつであるが、その首都「ダッカ」は、高層ビルの立ち並ぶ都会であった。航空会社のオフィスには、当然のようにコンピューターが置かれ、オンライン化されていた。しかしそのオフィスの外には、「ボクシーシ」(おめぐみを)と言いながら手を差し出す無数の子供達が待っていた。航空会社に出入りするような人は、金を持った人だという事で、狙いをつけているのだろう。このような人たちの中には、手や足が無い人がいる。障害を持った人ということで、なんとかお金を得ようということなのだが、恐ろしいことにそのような障害者は、自分に子供が生まれるとその手や足を切断し、子供も障害者に仕立てるという。障害者としてお金をめぐんでもらうという生き方以外考えられない環境なのだろう。その他、子供を抱きつつ「この子のためにおめぐみを。」と迫るパターンもあり、そういう人のために自分の子供をレンタルしてお金を得る人もいるという。まさにオドロキであった。
 交通手段は、日本の人力車に自転車をつなげたような「リキシャ」(語源は人力車だろうか)が主である。もちろん車も走っているが、一部の上流階級に限られている。このリキシャを1日動かしたとしても、得られる金は微々たるものであるらしい。リキシャも、自分のものではなく、元締めのような人から借りて営業しているわけで、儲けもかなり搾取されるような話であった。せっかく都会に出てきても、リキシャを引くかレンガを砕くか、そんな仕事しかないようで、むしろラクな「ボクシーシ」の道を選んでしまうのかもしれない。
交通手段は、日本の人力車に自転車をつなげたような「リキシャ」(語源は人力車だろうか)が主である。もちろん車も走っているが、一部の上流階級に限られている。このリキシャを1日動かしたとしても、得られる金は微々たるものであるらしい。リキシャも、自分のものではなく、元締めのような人から借りて営業しているわけで、儲けもかなり搾取されるような話であった。せっかく都会に出てきても、リキシャを引くかレンガを砕くか、そんな仕事しかないようで、むしろラクな「ボクシーシ」の道を選んでしまうのかもしれない。
経済面でもかなりオドロキだが、衛生面でもそうとうなオドロキであった。町中でも牛車がのんびりと走っているくらいだから、そこらじゅうに糞も落ちている。そんな所に出ている屋台の果物屋があった。皮を剥いて、並べようと思ったところで手がすべり、果物は糞だらけの地面の上に・・・それを拾い上げ、空き缶の中にためてあった水でジャブジャブっと洗い、そのまま何食わぬ顔で並べてしまう。私もかなり不衛生な方であるが、あれを食べたら、腹をこわすだろうと思った。
病院にも行ったが、病室のベッドの下には、どこから入り込んだのか数匹のネコが寝ていたし、ひとつのベッドに2人以上の人間があたりまえのように横たわっていた。ひとつの酸素ボンベから、理科の実験に使うようなビニール管が延び、それが何本にも枝分かれして、ベッドに届いていた。いわば、酸素のタコ足配線である。手術室にもドアなどなく、外界と全く遮断されることのないまま、ドクターが出入りする。ドクターは、もちろん免許制ではあるが、聴診器もろくに使えないようなかなりアヤシイドクターもいるという。むしろ人々は、それぞれの村の風習に従って、オマジナイのようなことをして、病気を直そうという発想が強いようだ。「今、ここで自分が病気になったら、もうダメだろうな・・・」と感じた。
ベンガル語が共通語となっているが、英語もある程度通じる。学校で学習しているので、ある程度学歴のある人なら、日本人の高校生か、それ以上くらいには英語を話せる。夜行列車の中で一緒になったベンガル人も、一生懸命私に英語で語りかけてきた。親切な人であったが、「親切なヤツがあぶない。」というような話を友達から聞いていたので、警戒はしていた。しかし彼が「手紙を書くから日本の住所を教えてくれ。」と言ってきた時には、断る理由もなく、つい日本の住所を教えてしまった。そのメモをカバンにしまうときの彼の「ニヤッ」とした顔を思い出すと、今でも寒気がする。そのあと彼は、「私はバングラデシュであなたに親切にした。だから私が日本に行ったら、私に親切にしてくれ。」と言った。これには異論はないので、「OK!」と答えたが、次に彼は、「日本に行ったら、私をあなたの召使いにしてくれ。」と言ってきた。これはさすがにOKできないので、「あなたは私の旅行中親切にしてくれた。だから、あなたが日本に来たら、あなたの旅行中、親切にしてあげよう。」と言ったが、これがなかなか通じない。むこうも必死に、「ユア、サーバント。アイ、ワーク、ハード。」などと、わけのわからないことを言ってくる。私も、はっきりした態度をとらなければと思い、「ノー。オンリー、サイトシィーイング!」と繰り返す。すると彼は諦めたのか、話題を変え、右の人差し指を立てて「ワン、ボーイ」と言った。次に左の人差し指を立てて「ワン、ガール」と言う。そしてその2本の指を目の前で何度が交わらせ、「ドゥー、ユー、ライク?」と聞いてきた。バングラデシュはイスラム教の国であり、そんな風俗的な場所はあり得ないはずなのに、あるところにはあるらしい。これにももちろん「ノー」とハッキリ答えた。その後もいろいろ英語で語った。英会話のトレーニングにはなったが、どうも後味の悪いものであった。彼は別れ際まで、「リター、リター。」と言いつつ、手紙を書くという身振りをしていたが、いまだに彼からの手紙は届かない。
 それにしても、バングラデシュの人たちは、よっぽど日本人(東洋人?)が珍しいらしく、駅のホームで電車を待っているだけでもたちまち数十人の人だかりができる。駅員のような人が追い払ってくれるのだが、またすぐに人だかりができてしまう。これは「お恵み」目当てで集まるボクシーシ軍団ではなく、単に興味から集まってくるようだ。もう少し愛想がよければいいのだが、みんな一様に黙ったまま、こちらを見つめている。初めはさすがに恐ろしかった。
それにしても、バングラデシュの人たちは、よっぽど日本人(東洋人?)が珍しいらしく、駅のホームで電車を待っているだけでもたちまち数十人の人だかりができる。駅員のような人が追い払ってくれるのだが、またすぐに人だかりができてしまう。これは「お恵み」目当てで集まるボクシーシ軍団ではなく、単に興味から集まってくるようだ。もう少し愛想がよければいいのだが、みんな一様に黙ったまま、こちらを見つめている。初めはさすがに恐ろしかった。
丸1昼夜かけてたどり着いた南部の町「シャトキラ」に、青年協力隊として「識字教育」や「女性の自立」のために力を注いでいる人がいた。男尊女卑を絵に書いたようなバングラデシュ社会の中で、女性の地位を高めるために、女手ひとつ(?)で活動していた。聞けばこの国の女性は、日本で言えば中学生くらいで、もう嫁に行くとか・・・そして、嫁入り道具のような意味合いで、持参金を持って嫁いで行くらしい。いまだに一夫多妻であるというのも驚いた。そして悪い男というのはどこにでもいるもんで、この持参金目当てに結婚し、たちまち離縁してしまうようなヤツもいるらしい。離縁された女性の方は、日本では考えられない話なのだが、「嫁の側に問題があったから・・・」ということで、もう2度と嫁にも行けず、かといって働く場所など女性にはなく、あとは誰かの召使いでもしながら生きて行くしかないという。
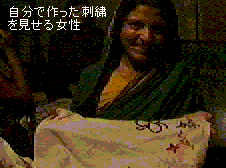 このような行き場のない女性を集め、ドレスメーキングの技術を身につけさせ、経済的に自立できるようにしようというのが、彼女の取り組みであった。昼はドレスメーキングの指導を、そして夜は、識字教育に取り組んでいた。ろくに電気も来ていない場所で、ランプの光の中で教室を開いていた。識字教育というのは、要するに字を読めるようにする指導である。つまり、そういう人たちは、ほとんど字を読めないのだ。女性ばかりではなく、昼はリキシャを引いているような男性も、この教室に参加していた。交通標識がわかるようになり、大変喜んでいるというような話だった。
このような行き場のない女性を集め、ドレスメーキングの技術を身につけさせ、経済的に自立できるようにしようというのが、彼女の取り組みであった。昼はドレスメーキングの指導を、そして夜は、識字教育に取り組んでいた。ろくに電気も来ていない場所で、ランプの光の中で教室を開いていた。識字教育というのは、要するに字を読めるようにする指導である。つまり、そういう人たちは、ほとんど字を読めないのだ。女性ばかりではなく、昼はリキシャを引いているような男性も、この教室に参加していた。交通標識がわかるようになり、大変喜んでいるというような話だった。
「それにしても、この少年・少女たちの瞳の輝きはなんなのだろう・・・」と、私は思った。恐らく日本では、小学生でさえ、このように瞳を輝かせて勉強してはいないだろう。10歳くらいの少年が、ベンガル文字の数字(アラビア数字ではない)の書き方、読み方を教えてくれた。お返しに、アラビア数字の日本語読みを教えてあげると、彼はたちまち覚え、キレイに発音してみせた。「学ぶ」ということは、本来楽しいことなんだと、改めて思った。すっかり忘れていた感覚であった。
シャトキラからの帰りは、丸1日かけて来た距離を、飛行機を使って1時間ほどで帰ってきてしまった。懐かしいプロペラ機の窓から下を見ると、あちらこちらに大きな湖のようなものが広がっているのが見えた。「雨期には国土の半分が水没する。」というのを思い出した。考えてみれば、ガンジス川の広大な三角州の上に作ったような国である。ただでさえ狭い国土が、雨期にはますます狭くなってしまう。ダッカでも、さっきまで晴れていたと思ったら突然のスコール・・・ということがあった。そうなると、あたり一帯水浸しになり、水たまりをみんな裸足で歩いていた。
この国の生活水準は、あきらかに日本より低い。贅沢はおろか、日々生きていくのが精一杯という人がたくさんいる。そういう意味では、ホントに日本に生まれたことに感謝しなければならない。しかし、あの識字教室の子供たちと、日本の子供たちを比べて考えたときに、「なに不自由ない暮らし」というのが、本当に幸福と言えるのか、疑問に思ってしまった。日本では、いつから勉強が苦痛になってしまったのだろうか。必要ないほど高度なことを勉強しているからということもあるだろう。学習結果を他人から評価されてしまうとか、学力を他人と比較されるからということもあるかもしれない。これは、日本の教育界が考えていかなければならない点だろう。まぁ考えても妙案はないと思うが・・・。