「西洋」というものを思い知る旅
・・・南アフリカ共和国
 南アフリカと聞いて、「この夏に、アフリカは暑いだろうなぁ・・・」と思った私は、まったくマヌケであり、実は南半球にある南アフリカ共和国は、今や真冬なのであった。さらに私を驚かせたのは、「世界で最も危険な都市ヨハネスブルグ」というニュースであった。聞けば、約3ヶ月の間に、殺人事件が5000件以上。計算すると、30分に1件以上は殺人事件が起こっている町であるらしい。これはハンパではない。私は、マジメに、「生きて帰ること」を、今回の旅行の第一目的と定め、身辺整理をした上で、旅立ったのであった。
南アフリカと聞いて、「この夏に、アフリカは暑いだろうなぁ・・・」と思った私は、まったくマヌケであり、実は南半球にある南アフリカ共和国は、今や真冬なのであった。さらに私を驚かせたのは、「世界で最も危険な都市ヨハネスブルグ」というニュースであった。聞けば、約3ヶ月の間に、殺人事件が5000件以上。計算すると、30分に1件以上は殺人事件が起こっている町であるらしい。これはハンパではない。私は、マジメに、「生きて帰ること」を、今回の旅行の第一目的と定め、身辺整理をした上で、旅立ったのであった。
ヨハネスブルグ空港のゲートを出ると、目の前に真っ黒な、それでいて目だけは異様に白く光らせた黒人たちが群がっていた。こう書くと、差別的な言い方に聞こえるが、実際、ヨハネスブルグに着いた頃は、黒人を見るだけでもコワイ気がした。なにせ、ヨハネスブルグ国際空港内でさえ、1日平均11件の被害届が出ているという。トイレに入って、となりに黒人が並んだだけでもコワかった。
30分に1件の殺人事件が起こっているというのは、ヨハネスブルグの中でもごく一部の「ダウンタウン」と呼ばれる地域である。実は、ソウェトという黒人居住区へのツアーの途中、このダウンタウンの中心部で、ワゴン車の中に取り残されてしまった。観光会社の案内役の黒人が、他の客を呼びに行ったほんの5分ほどの間なのだが、通りすがりの黒人がワゴンの中をのぞき込むわ、ワイパーをイタズラするわ、オソロシイことこの上なしであった。このダウンタウンを除けば、南アフリカ自体は、そんなに危険な国ではないようである。
ソウェトは、ヨハネスブルグ郊外にあった。悪名高いアパルトヘイト(人種隔離政策)は、5年前に黒人のマンデラ氏(現大統領)らの運動で完全に廃止されたが、たった5年間で人々の生活や心がそんなに変わるとは思えない。事実、ソウェトは現在でも黒人居住区であり、白人は住んでいない。このソウェトの中心部を通る道の名称を聞いて、また震え上がった。「キラーロード(殺人者の道)」というそうだ。とはいえ、ソウェト自体は、そう危険な場所ではなく、住んでいる黒人達の表情も明るい。貧富の差もかなりあり、バラックに住んでいる人から、かなりの豪邸に住んでいる人もいた。黒人でも商売のウマイ人は、アパルトヘイト政策下であっても裕福な生活をしていたようだ。
 幼稚園にも連れて行かれたが、バスを改造して作った教室から、子供たちがゾロゾロと出てきて、ケナゲにも我々の前で歌を歌ってみせるのだ。そして、まるで連携プレーのように、これまたケナゲな少女が、募金箱を持って我々の前に立つというわけだ。ソウェト全体がこんな感じであり、あっちでも募金、こっちでも寄付・・・という状況に追い込まれるように、ツアーは計画されているようだった。
幼稚園にも連れて行かれたが、バスを改造して作った教室から、子供たちがゾロゾロと出てきて、ケナゲにも我々の前で歌を歌ってみせるのだ。そして、まるで連携プレーのように、これまたケナゲな少女が、募金箱を持って我々の前に立つというわけだ。ソウェト全体がこんな感じであり、あっちでも募金、こっちでも寄付・・・という状況に追い込まれるように、ツアーは計画されているようだった。
ホテルは、ヨハネスブルグ郊外の住宅地にあったが、このあたりでは白人の方が多いくらいであり、見かける黒人は、公園の掃除などの、要するに「雇われた人」であった。こういう人たちは、みんな一様に「緑色のジャージ」を着ていた。実は南アフリカ国内どこでも、黒人の肉体労働者はこのジャージであった。人種差別はなくなったはずであるが、なんか差別的なモノを感じた。政策としての差別がなくなったとはいえ、経済的な格差がある以上、一般的な黒人の暮らしは、白人とは全く違うレベルなのであった。
とはいえ、南アフリカ航空のスチュワーデスには、黒人女性もたくさんいたし、オフィスなどにも、黒人女性が働いていたりした。これは5年前には考えられなかったことだそうだ。白人と同じホテルに宿泊するのも、5年前には許されなかったという。少しずつではあるが、確実に黒人達は南アフリカ共和国の正式な(?)国民になりつつあるようだ。もちろん「経済力がある黒人」に限られるが・・・。
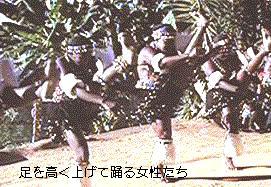 南アフリカは、典型的な多民族国家であり、同じ白人でもイギリス系もオランダ系もいるし、黒人だって多くの部族に分かれている。そのなかの、「ズールー族」という部族の様子を観光的に見せる「ぺ・ズールー」というところに行った。私は民族音楽に興味があるので、こういう場所は好んで行くのだが、このような「民族ショー」を見終わった後、いつもなんとなく後味の悪さを感じてしまう。台湾でも、やはり自分たちの部族の生活を見せるような観光地があった。自分たちの文化を、誇りを持って世界に広めている・・・のならいいのだが、こういうのはだいたい、自分たちの部族以外の資本家の手によって、観光目的で経営されているものであり、単なる「見せ物」という様相を呈している。ぺ・ズールーも同様で、上半身裸に腰ミノというような出で立ちの娘たち、オバサマたち、青年たちが、部族の踊りや歌を見せてくれた。最後はかならず、見物人も巻き込んで一緒に踊る・・・というのが、こういうショーのパターンであるが、実は私は、こういうのが最もニガテである。たまたま最前列で見ていたので、いつ誘いの魔手が迫るかと、正直言って生きた心地がしなかった。ところが、見物していた白人たちは、実に陽気に踊りの輪に加わり、完全に楽しんでしまっているのだ。黒人を差別するような様子もなく、実に自然に、黒人と共に踊っていた。「陽気な太っちょ白人おじさん」という感じであった。
南アフリカは、典型的な多民族国家であり、同じ白人でもイギリス系もオランダ系もいるし、黒人だって多くの部族に分かれている。そのなかの、「ズールー族」という部族の様子を観光的に見せる「ぺ・ズールー」というところに行った。私は民族音楽に興味があるので、こういう場所は好んで行くのだが、このような「民族ショー」を見終わった後、いつもなんとなく後味の悪さを感じてしまう。台湾でも、やはり自分たちの部族の生活を見せるような観光地があった。自分たちの文化を、誇りを持って世界に広めている・・・のならいいのだが、こういうのはだいたい、自分たちの部族以外の資本家の手によって、観光目的で経営されているものであり、単なる「見せ物」という様相を呈している。ぺ・ズールーも同様で、上半身裸に腰ミノというような出で立ちの娘たち、オバサマたち、青年たちが、部族の踊りや歌を見せてくれた。最後はかならず、見物人も巻き込んで一緒に踊る・・・というのが、こういうショーのパターンであるが、実は私は、こういうのが最もニガテである。たまたま最前列で見ていたので、いつ誘いの魔手が迫るかと、正直言って生きた心地がしなかった。ところが、見物していた白人たちは、実に陽気に踊りの輪に加わり、完全に楽しんでしまっているのだ。黒人を差別するような様子もなく、実に自然に、黒人と共に踊っていた。「陽気な太っちょ白人おじさん」という感じであった。
最後に、「写真をたくさん撮った人は、このザルの中にお金を入れてくれ・・・」というような説明があった。私は、ケチだからかもしれないが、こういうのがキライである。いかにも「見せ物」に対して「恵んでやる」というような行為に思えてしまうからだ。ところが白人たちは、チップの習慣に慣れているせいもあるのだろうが、実に自然に、ポンポンとお金を出していた。チップといえば、ソウェトのそばの喫茶店で、白人がチップを出すところを見て驚いてしまった。なんと、小銭を投げたのだ。もちろん地べたではなく、カウンターに投げたのだが、釣り銭をポーンと投げ、カッコ良く身をひるがえして店を出ていった。店員は、慌てて硬貨を押さえて「サンキュー」と言っていたが、なにも投げなくても、手渡してあげればいいじゃないかと思った。ま、たまたま手がすべったのかもしれないが、私にはいかにも、カッコ良くやっているように見えた。
どうも私には、チップという習慣自体が、なんか差別的に思えてしまう。日本では、現金を渡すことは、たとえお礼の気持ちであっても失礼とされる感がある。それを、100円程度のハシタ金を、「ホレ、やるよ。」とばかり渡すのは、どうも主人とメイドの関係を思わせてイヤだ。たとえば、仲の良い友達に親切にしてもらったとしても、彼らは友達にはチップは出さないだろう。やはり、主人とメイドのような関係においてチップを出すのである。人間として対等であるなら、契約なのだから、コーヒー1杯にはコーヒー1杯分の定められた料金を払えばそれでいいじゃないか・・・(ま、文化の違いに文句を言っても仕方ないが・・・)
ペ・ズールーに話を戻すと、実は大変に腹立たしいことがあった。ズールー族伝統の、縦穴住居のようなところに案内され、そこで酋長のような格好の人の話を聞いたのだが、その話が終わって、みんなが出ていった後、「写真を撮ろう!」ということで酋長が私を呼んだ。断る理由もないので、言われるままに酋長のとなりに座り、ズールー伝統の握手(あいさつ)の仕方を教わり、それを友達がビデオに写した。ま、そこまではいいのだが、その住居を出ようとした私の手を後ろから酋長がつかみ、手を差し出すのだ。金を要求しているわけだ。言わせてもらえば、私は無理に写真を勧められたのであって、断るのも失礼だと思って応じたのだ。金を取られる道理はない。しかし、そんなに無粋なこともできないから、仕方なしに硬貨を1枚、彼に手渡した。すると驚いたことに、彼は首を振りながら、さらに手を出すのだ。結局2枚の硬貨で勘弁してもらったが、これは、高校生の頃、不良少年にタカられて金を取られた時以来の不快感であった。こういう姿を見れば、もう完全に、彼らが自分たちの文化に誇りを持っているのではなく、開き直って「見せ物」に徹している連中であることは明白であった。腹立たしかったが、悲しくもあった。
 南アフリカで、もっともアフリカらしかったのは、クルーガー国立公園である。ヨハネスブルグにしろ、ケープタウンにしろ、完全に都市であり、高層ビルが立ち並んでいるわけだが、クルーガー国立公園の動物保護区は、完全に「サバンナ」という感じであった。ライフルを所持したガイドと共に、日産サファリ改造のオープンカーに乗り込み、草原を走り回ると、数々の動物を見ることが出来た。中でもエキサイティングだったのは、ナイトサファリであった。サーチライトの明かりの中で、ヒョウがインパラを捕らえたのだ。しかも、追ってきたハイエナ軍団から逃れるために、自分の体くらいあるインパラをくわえたまま、木にかけ上るというオマケがついた。ハイエナたちは、しばらくの間、木を見上げながら悔しそうに唸っていたが、やがて行ってしまった。ノドを噛まれ、息絶え絶えのインパラは、首をダランと垂らし、鼻の穴から水道のように血を流していた。このようなドラマが、目の前、ほんの5〜10メートルくらいのところで繰り広げられるのだ。その他、ゾウの親子とか、水牛、キリン、シマウマ、ライオン・・・あと、早朝の鳥の声の美しさも、心に残るものであった。1日しか滞在しないのは、あまりにももったいないと思った。1週間くらいいてもいいと思った。
南アフリカで、もっともアフリカらしかったのは、クルーガー国立公園である。ヨハネスブルグにしろ、ケープタウンにしろ、完全に都市であり、高層ビルが立ち並んでいるわけだが、クルーガー国立公園の動物保護区は、完全に「サバンナ」という感じであった。ライフルを所持したガイドと共に、日産サファリ改造のオープンカーに乗り込み、草原を走り回ると、数々の動物を見ることが出来た。中でもエキサイティングだったのは、ナイトサファリであった。サーチライトの明かりの中で、ヒョウがインパラを捕らえたのだ。しかも、追ってきたハイエナ軍団から逃れるために、自分の体くらいあるインパラをくわえたまま、木にかけ上るというオマケがついた。ハイエナたちは、しばらくの間、木を見上げながら悔しそうに唸っていたが、やがて行ってしまった。ノドを噛まれ、息絶え絶えのインパラは、首をダランと垂らし、鼻の穴から水道のように血を流していた。このようなドラマが、目の前、ほんの5〜10メートルくらいのところで繰り広げられるのだ。その他、ゾウの親子とか、水牛、キリン、シマウマ、ライオン・・・あと、早朝の鳥の声の美しさも、心に残るものであった。1日しか滞在しないのは、あまりにももったいないと思った。1週間くらいいてもいいと思った。
このように自然は素晴らしいクルーガー国立公園であるが、どうもなじめないのが、やはり白人の方々の行動であった。「角笛が鳴ったら、夕食の合図だからガーデンに来てくれ。」という説明だったので、角笛を聞いてさっそくガーデンに出かけると、従業員は働いているが、客の姿は全く見えない。しばらく待っていたが、夕食が始まる様子はない。仕方なしに、ロッジに戻ろうとする途中で、白人たちの高らかな笑い声が響いてきた。ロッジに併設されているバーの方からであった。要するに、角笛が鳴ろうが何が鳴ろうが、自分たちは今、バーで酒を飲んで楽しんでいるわけだ。だから、この楽しいひとときを、そのまま続けているわけだ。大切なのは自分たちが今楽しんでいることであり、その行為によって夕食の開始が遅れ、ハラを減らしたジャパニーズがオアズケを食っているかもしれないことなどは、あまり考えないのだろう。白人というのはホントに「楽しむ」ことが上手である。そして、悪く言えば自己中心的である。
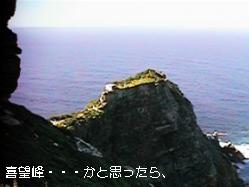 ケープタウンにも行った。テーブルマウンテンという、平らな山の麓に町が広がっていた。有名な喜望峰は、町からかなり離れていて、1日がかりの観光である。喜望峰と言えば、地理や歴史で学習しているし、アフリカの南端ということで、とりあえず行ってみようと思ったわけだが、行ってみると何のことはない。要するに岬である。規模は、さすがに大きかったが、足摺岬の10倍くらいをイメージすればいいだろう。しかし、残念なことにここはアフリカ南端ではなかった。バスコダガマが、そう誤解していただけで、実際の南端は、ずっと東の方のアグレス岬というところらしい。確かに、地図帳を開けば一目瞭然である。これはけっこう知らない人が多いのではないかと思った。さらに、これは後から知ったのだが、私が喜望峰だと思っていたのは、その隣のケープポイントという岬で、その展望台から右の方に見えたサエナイ低い出っ張りが、喜望峰だったのであった。
ケープタウンにも行った。テーブルマウンテンという、平らな山の麓に町が広がっていた。有名な喜望峰は、町からかなり離れていて、1日がかりの観光である。喜望峰と言えば、地理や歴史で学習しているし、アフリカの南端ということで、とりあえず行ってみようと思ったわけだが、行ってみると何のことはない。要するに岬である。規模は、さすがに大きかったが、足摺岬の10倍くらいをイメージすればいいだろう。しかし、残念なことにここはアフリカ南端ではなかった。バスコダガマが、そう誤解していただけで、実際の南端は、ずっと東の方のアグレス岬というところらしい。確かに、地図帳を開けば一目瞭然である。これはけっこう知らない人が多いのではないかと思った。さらに、これは後から知ったのだが、私が喜望峰だと思っていたのは、その隣のケープポイントという岬で、その展望台から右の方に見えたサエナイ低い出っ張りが、喜望峰だったのであった。
ケープタウンのホテルでは、ビールを飲み比べたりした。「CASTLE」という銘柄のビール(むこうでは「コステル」と呼んでいた)が、たいへんおいしかった。残念ながら、日本でお目にかかったことはないし、インターネットの「ワールドビール」などのページでも見たことはない。あれば、取り寄せたいくらいである。
今回の旅行では、南アフリカ国内と、ビクトリアの滝(ジンバブエ)の間を、すべて飛行機で移動したので、日本からの往復を除いても8回のフライトがあった。その都度空港のチェックインカウンターのお世話になるわけだが、ここでもまた、なじめない白人に出会ってしまった。チェックインカウンターのオネエサンにしつこく注文をつけているのだ。チェックインなんて、1〜2分で済むはずなのに、もう5分以上交渉している。その人の後ろには、5〜6人の人が順番を待っているのだ。一段落したと思ったら、今度は家族を呼び寄せ、家族会議を始める。その後、またあらためて交渉を開始するのだった。その間、後ろに並んだ人たちは、文句も言わずに待っている。私はすっかりシビレを切らしてしまった。
そうかと思うと今度は機内での話。飛行機に乗り込んで狭い通路を歩き、自分の席を見つけたら、普通の日本人の感覚なら後ろに続く乗客のジャマにならないように、とりあえず席につくなり、横に退くなりすると思うのだが、白人の方々は違っていた。太っちょの体で通路を塞ぎ、いつがキリともなく、自分の荷物を棚に上げているのだ。その間、後続の乗客は通路で足止めを食わされる。そういう光景が、あちらこちらで展開しているのだった。ここでもまたシビレを切らしてしまった私は、「他人を待たせることに鈍感な白人の方々は、やはり自己中心的だ。」と思ってしまうのであった。
この異文化拒絶、国粋主義的傾向は、旅行の間中続いたが、最終目的地のダーバンのホテルにおいて、なんとなく白人の行動が理解できるようになってきた。ホテルのレストランで夕食をとろうとした時のこと。レストランは非常に混雑しており、我々は名前を控えられ、「順番が来たら呼ぶから、隣で飲んでいてくれ。」というようなことを言われた。隣にはショットバーがあり、白人の方々の陽気な笑い声が響いていた。実は私たちは、ここで1時間近く待たされてしまったのだが、白人の方々は、そんな待ち時間を全く苦にしている様子はなかった。つまり、彼らは次のように考えているのではないだろうか。「レストランは混んでいる。これは仕方がない。食事はゆっくり楽しみたいわけだから、さっさと食べて席を空けろ・・・なんて考えない。とすれば、自分たちは待つしかない。どうせ待つなら、待つ時間も楽しい時間に変えてしまおう。そして、自分たちの順番が来たら、他の人のことなんて考えず、ゆっくりと自分たちの食事を楽しもう・・・」つまり、他人を待たせることも平気だが、他人から待たされることも平気なのだ。だから、一応スジは通っているのだ。もちろん、私にはなじめないが・・・
南アフリカ旅行記から離れて、いろいろと「白人感」を書いてきたが、私が今回の旅行で最も印象に残ったのが、実はこの「西洋文化圏での生活体験」なのであった。彼らはアタリマエに英語で話しかけてきた。今までに行った韓国や台湾、バングラデシュなどでは、お互いに努力して会話を成立させようという気持ちが感じられた。自国語はもちろん、相手の国の言葉から英語からボディーラングェージまで持ち出して、コミュニケーションをとろうとした。しかし白人たちは、「国際共通語」をふりかざし、通じなければ両手を開いて肩をすくめるのみであった。(・・・というように、私には感じられた。英語が使えないために、おおいに卑屈になっていたので、そのように感じたのかもしれないが・・・)
考えてみれば、世界各地で英語が使われているのは、英語を話す人種が、歴史上のある時期に世界の色々な場所を侵略し、現地人を迫害し、その土地を自分のものにしたからであろう。南アフリカだけの話ではない。アメリカをはじめとして、オーストラリア、ニュージーランド・・・ヘタをすれば、アフリカやアジア地域などは、みんな西洋人の支配する国であったかもしれないのだ。日本人も、過去に行った他国侵略の歴史をしっかりと学ぶべきであるが、西洋人は、いまだに世界各地を侵略したままになっていることを、果たしてしっかりと学んでいるのだろうか・・・。
今までの私は、「日本は戦争で悪いことをした。西洋人は紳士的だ。」という、単純な、俗に言う「自虐的歴史観」であった。もちろん、いまさら第2次世界大戦における日本の行動をを正当化しようとは思わないが、少なくとも今までよりは深いレベルで、世界を見られるようになった。とはいえ、南アフリカは、黒人のマンデラ大統領を中心に、全人種融和路線での新しい国作りが始まっている。過去のことをほじくり出すのではなく、将来のことを現実的に考えていくべきなのだろう。元々の居住者である黒人たちの生活水準が、はやく白人並になることを祈るばかりである。
注:たった1週間の旅行において感じた私見を書いたものです。白人や黒人をひとまとめにして性格を表したような記述がありますが、もちろん白人にも、黒人にも、いろいろなタイプ、いろいろな考え方の人がいるだろうことは承知しています。