死者の声を聞く旅・・・恐山
恐山といえば、イタコの口寄せで名高い。イタコと呼ばれる霊媒師が、死者の魂を自分に乗り移らせることで、死者の声を代弁するというのが、イタコの口寄せである。私は、死後の世界など信じていなかったので、このイタコの口寄せも、いいかげんなもんだろうと考えていた。しかし、そんな考えは恐山に向かうバスの中で、簡単に打ち砕かれてしまった。とは言っても、バスの中で心霊現象に出くわしたわけでもイタコに出会ったわけでもない。下北鉄道の田名部駅から恐山に向かうバスは、恐山に関する観光案内のようなものを、車内放送で流していた。その話を聞いて、私は心打たれてしまったのだ・・・
病気がちで、ほとんど家から出ることもなかった娘が、若くしてこの世を去った。残された両親は、何一つ楽しいことを知ることもないまま死んでいった娘を大変不憫に思い、いつか着ることもあるだろうと思って作っておいた娘の花嫁衣装を抱いて、恐山に向かう。「娘は、あの世で幸せに暮らしているのだろうか・・・一人で寂しい思いをしているのではないだろうか・・・」しかし、イタコに乗り移った娘は、こう語るのだった。「私は、こちらの世界で毎日楽しく暮らしているから安心してほしい。お父さん、お母さんも、体に気をつけて、元気に暮らしてほしい・・・。」その後、両親は地獄谷の方を散歩し、娘の衣装を岩に掛けて、それを娘だと思って、3人で記念写真を撮った。家に戻って、写真を現像してみると、なんと、その岩肌には、うれしそうに微笑む娘の顔が写っていたのだった・・・。
だいたい、このようなストーリーだったと思う。私は、「そうか、そういうことか!」思った。この両親は、娘を不憫に思っている。何かしてやりたいのに、結局何もしてやれなかったという後悔がある。きっと毎日、娘のことを考えては、辛い日々を送っていたに違いない。しかし、イタコと出会い、幸せそうな娘の言葉を聞いて、どれだけ気持ちが楽になったことだろう。岩肌に写っていた娘の姿だって、もしかしたら他人には、ただの岩の模様に見えるのかもしれない。でも、この両親には、娘の笑顔に見えるのだ。両親にそう見えるなら、それで十分なのだ・・・。これが、イタコの口寄せの意味なんだと思った。イタコの語る死者の声が、この世に生きる者の心を救うのだ。私だって、もしも自分が愛して止まない人が突然この世を去ったら、恐山を訪れ、イタコに頼んで愛する人の声を聞きたいと思うかもしれない。私はすっかり、恐山という場所に親しみを感じてしまっていた。そのオソロシげな名前とは裏腹に・・・。
私は、途中「冷水峠」で一人バスを降りた。ここには、不老水とも言われる湧水があった。非常に冷たくておいしい水であった。この峠を境に、いよいよ霊界に入ることになる。誰も通らない、車さえほとんど通らない坂道を降りていくと、眼下に宇曽利山湖という湖が見えてくる。この湖のほとりに、恐山菩提寺があり、その境内に、地獄谷とか、賽の河原などの荒涼たる風景が広がっていた。
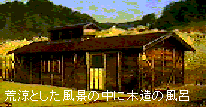 その夜は、恐山菩提寺の宿坊に宿泊した。質素な精進料理をいただく。「我々は、この世に生きる物の命を食べて生きている。食事が出来ることに、感謝の気持ちを持たなければいけない・・・」という話をうかがう。これも貴重な体験であった。
その夜は、恐山菩提寺の宿坊に宿泊した。質素な精進料理をいただく。「我々は、この世に生きる物の命を食べて生きている。食事が出来ることに、感謝の気持ちを持たなければいけない・・・」という話をうかがう。これも貴重な体験であった。
菩提寺の境内には温泉が4つも湧いていた。夜中に一人下駄をならして、風呂に行ってみる。湯船につかると、ほったて小屋のような風呂場の窓から何本もの巨大な卒塔婆が見える。「そうだ。ここは霊界だったんだ・・・」と、あらためて思った。しかし、なぜか「恐怖」ではなく、なんとも言えない安心感があったのは、まことに不思議なことであった。
 この旅行は、私にとって初めての「一人旅」であった。夜行列車「八甲田」で、朝青森に着き、恐山に一泊して、翌日の「八甲田」で戻って来るという強行軍であったが、本当にいろいろな経験をした。一人旅というのは、何人かで旅するのと違って、多くの人との出会いがある。車を使わずに電車やバスで移動する場合は、特にそうである。行きの八甲田は、乗務員も驚くほどの混み方で、通路に座るのがやっと・・・ヘタをすれば、通路に立ったまま寝ている人もいたほどであった。でも、この極限状況の中、何人かの人たちと友達になった。もちろん、その場限りの友達であり、その後の交流があるわけではない。でもまたそれがイイのだ。恐山菩提寺に着いたとき、昨夜の八甲田で友達になった女性の二人組に、偶然再会した。記念写真を撮ったのだが・・・彼女たち、今頃どうしているだろうか・・・
この旅行は、私にとって初めての「一人旅」であった。夜行列車「八甲田」で、朝青森に着き、恐山に一泊して、翌日の「八甲田」で戻って来るという強行軍であったが、本当にいろいろな経験をした。一人旅というのは、何人かで旅するのと違って、多くの人との出会いがある。車を使わずに電車やバスで移動する場合は、特にそうである。行きの八甲田は、乗務員も驚くほどの混み方で、通路に座るのがやっと・・・ヘタをすれば、通路に立ったまま寝ている人もいたほどであった。でも、この極限状況の中、何人かの人たちと友達になった。もちろん、その場限りの友達であり、その後の交流があるわけではない。でもまたそれがイイのだ。恐山菩提寺に着いたとき、昨夜の八甲田で友達になった女性の二人組に、偶然再会した。記念写真を撮ったのだが・・・彼女たち、今頃どうしているだろうか・・・
 尻屋崎という岬では、「この季節特有の現象・・・」というのを見た。膨大な数のイワシの群れが、なぜか磯に打ち上げられ、行き場をなくしてしまうのだった。地元の人は、スーパーのビニール袋を片手に、そのイワシを、まるで「拾う」ように集めていく。瞬く間にビニール袋は一杯になる。その現象を説明してくれた地元のおばさんの説明も、言葉がわかりにくかったが、人の良さそうな感じであった。
尻屋崎という岬では、「この季節特有の現象・・・」というのを見た。膨大な数のイワシの群れが、なぜか磯に打ち上げられ、行き場をなくしてしまうのだった。地元の人は、スーパーのビニール袋を片手に、そのイワシを、まるで「拾う」ように集めていく。瞬く間にビニール袋は一杯になる。その現象を説明してくれた地元のおばさんの説明も、言葉がわかりにくかったが、人の良さそうな感じであった。
また、尻屋崎では、杭の上に不安定にカメラを載せ、セルフタイマーで記念写真を撮ろうとしている女の子の二人連れがいた。私は、気軽に「撮ってあげましょうか?」と声をかけ、写真を撮ってあげたのだが、思えば、普段の自分らしからぬ行動だった。
青森駅で、帰りの八甲田を待っている時間、駅前の寿司屋に入った。板前さんと話をした。隣に座っていた「通」っぽい人とも話をした。「一人旅」をすることで、こんなに自分が自由になるとは思わなかった。思えばこの旅が、私の「旅」の始まりであったのだ。